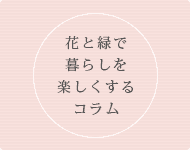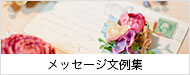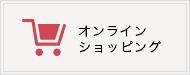最短で
07月31日
にお届けできます。
対象商品をさがす
母の日のお花として有名なカーネーション。赤やピンク以外にも、黄・オレンジ・白・グリーンなど色数も豊富で育てやすく、切り花以外にも、鉢植えで自宅で気軽に楽しむことができます。
ここでは、これからカーネーションを育てたいと考えている方向けに、カーネーションの基本情報から品種・種類、育て方・植え替えのポイント、歴史・由来やよくある質問まで、基本的な栽培方法やお手入れのコツをご紹介していきます。
カーネーションとは?基本情報について

カーネーションはナデシコ科ナデシコ属の多年草。開花時期は2~5月ですが、ハウス栽培が盛んでお花屋さんには1年を通じて流通しています。長年の品種開発によってさまざまな色や形を持ち、バリエーション豊かで扱いやすい花であることから、アレンジメントや花束などに使用されることも多いです。そのため切り花のイメージが強いですが、初心者でも育てやすい花鉢も高い人気があります。
カーネーションの品種・種類
カーネーションは切り花用の品種と、地植え・鉢植え用の品種とに分かれます。また花の付き方として、1本の茎に1つの花が咲く「スタンダード」タイプと、茎が数股に分岐して数輪の花を咲かせる「スプレー」タイプとに区別されます。
カーネーションの咲き方としては、花びらの縁がギザギザになっていてもっともメジャーな「剣弁咲き」、通常より細い花びらの先端が鋭く切れ込んでギザギザになっている「極剣弁咲き(スター咲き)」、花びらの縁にギザギザがない「丸弁咲き」、花びらが重ならずに咲く「一重咲き」などの種類があります。
このようにとても多様な種類・品種を誇るカーネーションですが、そのぶん、まずどんな品種から選べばよいか迷ってしまう方もいらっしゃるでしょう。次に、カーネーションでおすすめの人気品種をご紹介しましょう。
■【地植え・庭植え向き】ローズドメイカーネーション
カーネーションは香りが良いお花で、もともとはハーブの1種でもありました。19世紀以前から存在し、特に香りの良いカーネーションのことを「オールドファッションカーネーション」と呼びますが、ローズドメイカーネーションもその1つです。縁がギザギザとしたフリンジ状で、可愛らしいシェルピンク色のお花から甘い香りを漂わせます。背丈が40cmほどになり、半耐寒性で丈夫なので、地面に直接植える地植えに向いています。
■【鉢植え向き】サッキーネ
サッキーネはポットカーネーションの1つ。ポットカーネーションとは、鉢植えに適したサイズとなるようカーネーションを改良した園芸品種のことです。背丈は比較的小ぶりですが、葉が密に茂り、次々につぼみを付けてたくさんのお花を咲かせ、室内で管理しやすいようになっています。サッキーネは赤やピンクの花びらに白い縁取りがあるものが主で、厳寒期にはマイナス8度になる環境で生まれたため、寒さに強く育てやすい品種です。
母の日ギフトをはじめ、贈り物にもぴったりなカーネーションですが、プレゼントする際にカーネーションをさらに楽しむための方法については、 こちらの記事 も参照してください。
カーネーションの育て方とポイント
カーネーションの栽培環境・場所・日当たりについて
カーネーションは日当たりがよく乾燥した状態を好み、高温多湿や多雨には弱い品種です。つぼみを多く付けるため、日照不足は特にNG。また葉が多く茂るポットカーネーションは特にカビが原因の病気になりやすいため、日当たりと風通しがよく、雨が続くときは軒下など雨を避けられる場所に置いてください。
耐暑性・耐寒性は高いですが、夏場の高温期には水やりなどによる蒸れに注意します。ベランダなど直接太陽が照り付ける環境では、スノコやレンガを鉢の下に敷いて地面から離すと良いでしょう。ガーデニング用品として販売されている日よけシートを用いるのもおすすめです。このとき肥料を与えてしまうと、病気の原因になるため注意してください。また、気温が0度を下回るような冬場の低温期には、できれば室内に取り込み、強い寒風に直接当てないようにします。
カーネーションの水やりについて
カーネーションの根元の土が乾いてきたら、鉢底から水が流れ出るくらいたっぷりと水を与えてください。乾燥を好む品種ですが、つぼみが出る時期や伸長期には、日差しとともに日頃より多く水分を必要します。地植え・庭植えの場合は特に水切れに注意しましょう。
ただし水のあげすぎは病気などの原因になります。土の状態、カーネーションの生育状態を見ながら、適切に水を与えてください。また、葉や花に水がかかると蒸れの原因になるため、なるべく根元のほうに水をかけるようにしてください。
カーネーションの肥料について
つぼみや花全体に栄養を届けるため、真夏を除いて定期的に肥料を与えます。緩効性の置き肥であれば月に1回ほど、土のなかに半分埋め込むように与えてください。5号鉢であれば2~3粒が目安です。液体肥料の場合は月に3回ほど与えます。
成長が盛んな3~5月、9~10月には、与える肥料をやや多めにしてもOK。庭植えの場合も、同様の肥料を鉢植えよりもやや少なめに施します。
カーネーションの植え替えの仕方とポイント
カーネーションの土づくりについて
多湿を嫌い、栄養を多く必要とするカーネーション。初めてカーネーションを育てる方の場合は、市販されている草花用の培養土を使うと、簡単にバランスの良い環境を作ることができておすすめです。
鉢植えの場合、小粒赤玉土7:腐葉土3を基本として、少量の苦土石灰を混ぜて作ります。水が土に染み込みにくいときは、少量の川砂を混ぜてもよいでしょう。
カーネーションの植え付け・植え替えについて
カーネーションの植え付けは鉢植えと地植え(庭植え)で手順が少々異なります。
■鉢植えの場合
植物を育てることにあまり慣れていない方は、鉢植えを選ぶのがおすすめです。3~5月もしくは、9~10月頃が鉢植えに適した時期。以下の手順で行いましょう。
- 育苗ポットや現在の鉢よりひと回り大きな鉢を用意する
- 株を取り出し、根に付いた土を揉んで落とす
- 新しい鉢に鉢底石と土を入れる
- 鉢の1/3ほど土を入れ、株を中心に置いて周りに土をかけていく
- 鉢の縁から2~3cmほど下まで土を入れたら肥料を入れる
- 水をやり、日当たりと風通しのよい場所に設置する
■地植えの場合
地植えは、鉢植えに慣れてきた方におすすめです。庭などにカーネーションを地植えする際は、西日が当たらない暖かい場所を選んで行います。涼しく快適な気温と湿度の秋に行うのが適切です。以下の手順で行いましょう。
- カーネーションを植える予定の場所で土を掘り起こし、腐葉土や堆肥を混ぜて1週間ほど寝かせる
- 1週間後、株と株のあいだを30cmほど空けて、株よりもひと回り大きなサイズで穴を掘る
- 植え付ける株を取り出し、根に付いた土を揉んで落とす
- 穴の中心に株を置いて周りに土を被せる
- 水やりをする
一般的にカーネーションの開花時期は4月後半~6月と10月~11月ですが、お花が終わったあとに新しい用土へ植え替え、切り戻しを行う必要があります。これによって、お花を咲かせ終えて疲れている株に新しい栄養を行き渡らせると同時に、夏場の高温期も蒸れを防いで涼しく過ごせるようになり、また元気につぼみを付けることができるため、必ず行うようにしましょう。植え替えも植え付けと同様の手順です。切り戻しについては、この2つ後の章で詳しくご説明します。
カーネーションの増やし方
カーネーションは「挿し芽(挿し木)」という方法で増やします。古くなった株は生育が悪くなり花姿も乱れてくるので、お花の終わった時期に挿し芽をして新しい苗をつくります。以下の手順で行いましょう。
- 育苗ポットと受け皿、挿し木用の土を用意する
- メインの茎から出ている若い茎を、10cmほどの大きさで切り取る
- 先端に付いている葉を数枚だけ残して取り除く
- 切り取った若い茎の切り口を数日間に渡って水に浸ける
- 育苗ポットに挿し木用の土を入れ、茎の切り口を潰さないよう挿す
- 土の乾燥防止に受け皿に水を溜め、半日陰の場所で管理する
- 1ヶ月ほどで根が出るので、鉢や庭に植え替える
カーネーションの花がら摘み・切り戻しについて
カーネーションには「花がら摘み」と「切り戻し」という作業が欠かせません。
■花がら摘み
「花がら」とは、咲き終わって萎れたお花のことを指します。花がらは腐ってカビなどの原因となるため、早めに摘み取ってしまうことが必要です。また花がらをこまめに取り除くことで他の部位に栄養が回るようになり、新たな花芽が育ちやすくなります。花がらを取る際、側のつぼみや花を傷めないよう注意してください。
■切り戻し
ひととおりお花を咲かせ終わった茎には「切り戻し」という作業を行います。茎の葉のつけ根(節)から出ている脇芽やこれから芽吹きそうな節を確認して、これらは残しつつ、下から数えて2節程度の短さまでバッサリと切り落とします。また茎の本数が多く、混雑した印象を受けるのであれば、根元から間引いてしまいましょう。これらは植え替えと同時に行います。切り戻しによって風通しが良くなり、湿気の多い梅雨や夏の暑さ・蒸れへの対策となります。
カーネーションのかかりやすい病気・害虫
カーネーションの気をつけたい病気
カーネーションを育てるうえで、特に気をつけたい病気は以下のものです。
■灰色カビ病
灰色カビ病は、花びらや葉にカビが生えることによって葉が灰色に変色し、次第に枯れていく病気です。
■立枯病
茎が外側から内側へ褐色に変色し、ピンク色やオレンジ色のカビが生えてきて茎の内部にまで至り、枯れていく病気です。
■斑点病
こちらもカビによって葉や茎に黄色や褐色の斑点が出て萎れていく病気です。病気が進行すると斑点のうえに黒いスス状のカビが出てきます。
■ウイルス病
カーネーションに潜在していたり、アブラムシが媒介するウイルスによって白や緑・黄緑色の斑点やモザイク、壊疽などが出る病気です。生育が悪くなったり花びらが奇形になる場合もあります。ハサミなどの刃物を通じて伝染する場合もあります。
カビは湿気の多い環境で繁殖しやすいので、風通しの良い場所に置き、枯れた花や葉はすぐに取り除いてください。ウイルス性の病気を防ぐには、異常のない健康な株から増やすこと、アブラムシ対策を行うことです。もし発生してしまったら他の株や鉢に伝染させないよう、病気が出た部分を切除して薬剤を散布します。それでも広がるようであれば株ごと処分が必要です。
カーネーションの気をつけたい害虫
カーネーションを育てていくなかでは、以下の害虫に気をつけましょう。
■アブラムシ
葉から栄養を吸って株を弱らせるほか、ウイルス病などの病気の原因になることもあります。
■ハダニ
葉の裏側を中心に蕾にも付く虫で、葉が掠れたような色に変色することで発覚する場合が多いです。
アブラムシもハダニも、カーネーションに限らず多くの植物に付く害虫です。アブラムシは早期発見が大事。日頃から注意しておき、見つけ次第、薬剤を撒いて駆除します。ハダニは温度が高く乾燥した環境で発生するため、風通しの良い場所に置き、霧吹きなどで葉にこまめに水を与えて防ぎます。殺ダニ剤などの薬剤も有効です。
カーネーションの歴史や由来

カーネーションの原産地は南ヨーロッパおよび西アジアの地中海沿岸で、この地域に生えていた原種に他の野生種が交雑し、現在のカーネーションの姿になったと言われています。カーネーションはイスラム社会でも、バラやチューリップと並んでアラベスク模様と呼ばれる幾何学装飾にも使われていました。17世紀にはイギリスやオランダで盛んに品種改良が行われ、日本にはオランダを通じて江戸時代初期以前に輸入されたと伝えられています。まさに世界中で愛されているお花です。
1910年にはアメリカ合衆国のウェストバージニア州でアンナ・ジャービスという女性の呼びかけによって母の日が始まりましたが、その際、彼女が尊敬する亡き母に白いカーネーション捧げたことから、亡き母には白の、存命の母には赤のカーネーションを贈ることが母の日のシンボルと認識されるようになりました。
カーネーションという名前の由来には諸説ありますが、有力なものは2つ。ラテン語で肉を意味する「carn」と同じ色の花であることから名づけられたという説と、16世紀後半~17世紀のイギリスで、冠を飾る花(coronation flower)として使われていたことから、戴冠式を意味する「coronation」が転じて「carnation」となったという説です。
また学名の「Dianthus caryophyllus」は、ギリシャ語で「神(ジュピター)の花」を意味する「Dianthus」と、同じくギリシャ語でクルミの葉を意味する「 caryophyllus」とが組み合わされてできています。
カーネーションの育て方に関するよくある質問
Q&A①:咲くつぼみと咲かないつぼみがあります。理由は何ですか?
カーネーションはつぼみをたくさん付けるように改良されていますが、その分、つぼみからお花を開かせるまでの体力も多く必要とします。咲かないつぼみが出る理由は、日照が足りなかったり、株が弱っていてパワーが足りなかったりといったものが主です。指でつぼみを摘まんでみた際、中身が詰まっておらずスカスカだったら切除する。あるいは、萎れてきたお花は早めに取り除くなどして、元気なつぼみや新芽に充分栄養が回るようにしてあげてください。
Q&A②:葉の下の方から黄色く枯れてきてしまった。何が原因でしょうか?
カーネーションの鉢を、購入したりもらったりした際のラッピングで包まれたままの状態にしていないでしょうか?もしくは、風通しの悪い環境に置いていないでしょうか。風通しが悪いと、蒸れによって弱ったり、カビなどが発生して病気にかかることが多くなります。素敵なラッピングは名残り惜しいですが、カーネーションの健康のためには、手元に来た時点ですぐに外して鉢だけの状態にしましょう。さらに換気のできる場所に置いて、枯れてきたお花や葉はこまめに取り除くようにしてください。
カーネーションの花を選ぶなら日比谷花壇
日比谷花壇 では、カーネーションをはじめとした多くの鉢植えやアレンジメント、花束などを幅広く取り揃えています。
記念日やお祝いごとの贈り物として選ぶ際には、お花のスタイル別や贈る目的別、予算別の検索が便利。最短翌日着のクイック配送や海外配送などのサービスもございます。また、母の日にぴったりのカーネーションを選ぶには 「母の日特集」 をご覧ください。カーネーションを使ったアレンジメント、花鉢、花束、スイーツやグルメ・日用品とのセットアイテムを、お母さんの好みに応じてお選びいただけます。
またご自宅でも気軽にお花を楽しんでいただけるよう、その時期に見頃を迎える旬のお花を日比谷花壇のバイヤーがセレクトした 「バイヤーおまかせフレッシュ便」 、 自宅でお花を楽しむためのコツやアイディア などもご用意しています。
ぜひ、大切な人やご自身で楽しむのにぴったりのフラワーギフトを探してみてください。
まとめ
ここまで、これからカーネーションを育てたいと考えている方向けに、カーネーションの基本情報から品種・種類、育て方・植え替えのポイント、歴史・由来やよくある質問まで、基本的な栽培方法やお手入れのコツをご紹介しました。
さまざまな色や形があり、見ているだけで心躍るカーネーション。切り花以外にも鉢植えや地植えにすることで、長く楽しむことができます。こちらの記事を参考に、ぜひお気に入りのカーネーションを迎えて楽しんでみてください。