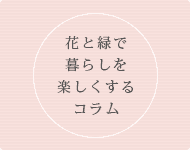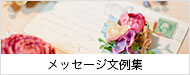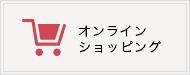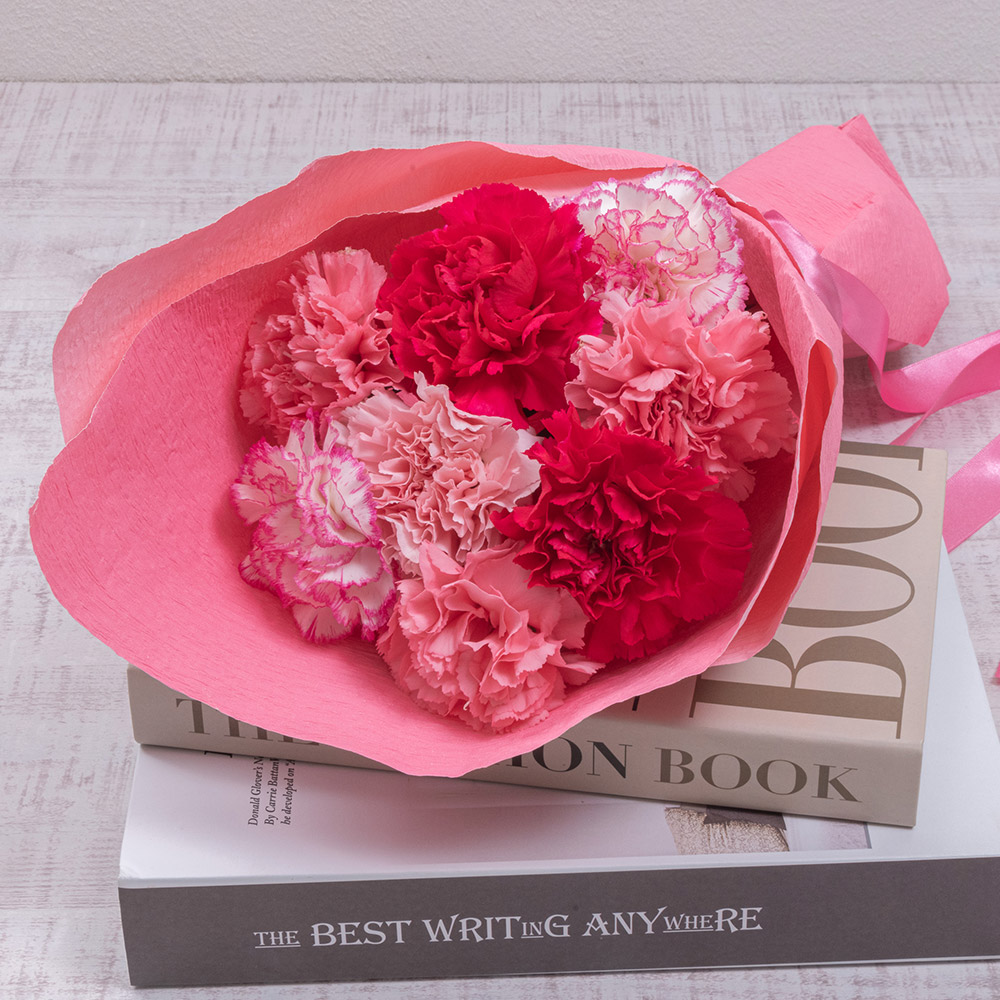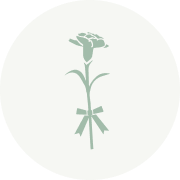最短で
07月31日
にお届けできます。
対象商品をさがす
最近ではインテリアとして観葉植物の人気が高まっていますが、特に他にない独特の魅力を持ったサボテンが根強い人気です。ここではこれからサボテンを育てたいと考えている初心者の方向けに、サボテンの歴史や由来・品種・特徴のほか、水やり・肥料・植え替えなど、基本的なお手入れの方法やコツをご紹介していきます。
サボテンとは?基本情報について
そもそも、サボテンとはどんな植物なのでしょうか。まずは基本情報を見ていきましょう。
サボテンとは別名「シャボテン」、和名では「仙人掌」「覇王樹」などとも呼ばれ、サボテン科に属する植物の総称を指します。アメリカ・メキシコから中南米を原産とし、砂漠などの乾燥した高温の土地、標高の高い場所といった過酷な環境で生息しています。このため、茎や根に水と栄養を蓄えるような構造になっています。
ボールのように丸いものや平べったいもの、巨大になるものなど形態はさまざまですが、最大の特徴は、全体を覆う尖ったトゲ。このトゲは葉が変化したもので、「刺座(しざ)」「アレオーレ」と呼ばれる白い綿毛のような特有の器官から生えています。茎や根に水などを溜められる植物のことを「多肉植物」と呼び、サボテンも多肉植物の一部に分類されますが、他の多肉植物はこの刺座を持っていないため、サボテンだけが「サボテン科」として区別されます。
サボテンの歴史・名前の由来
「サボテン」の名称を使っているのは日本のみです。中南米を原産とするサボテンは、16世紀後半から17世紀にかけて、当時世界中で貿易を行っていたポルトガルによって日本に持ち込まれたとされています。彼らは団扇のように平たい「ウチワサボテン」の切り口で汚れを拭いたり、樹液を石鹸(ポルトガル語でシャボン)として使っていたため、「石鹸のようなもの」を意味する「石鹸体(さぼんてい)」と呼ばれるようになった、という説があります。そのため1960年代までは「シャボテン」と表記する事が多く、現在でも「サボテン」と併用されています。
英語ではサボテンを「Cactus(カクタス)」と呼びます。これは古代ギリシア語で棘だらけの植物を指す「カクトス」という単語が、ラテン語で同様の意味を持つ「Cactus(カクトゥス)」と合わさって取り入れられたものです。
サボテンの品種・種類
サボテンは丸型や柱状などさまざまな形状をしており、花を咲かせたりトゲがないものがあるなど、バリエーションも豊富。ここでは人気の品種・種類をご紹介します。
■ウチワサボテン
平たく丸い団扇のような茎が連なっていて、日本での「シャボテン」という名前の由来にもなった品種です。茎の表と裏には鋭いトゲが生えています。実と茎は栄養価が高く、海外では食用にもされています。ウサギの耳にも見えるそのユニークな形状から人気が高く、小型で可愛い「金烏帽子(キンエボシ)」、寒さに強い「大丸盆」、トゲが少なく安全な「墨烏帽子(スミエボシ)」などを特によく見かけます。
■柱サボテン
柱状に伸びるサボテンの総称を「柱サボテン」と言います。サボテンといえばこの柱サボテンがイメージされることが多く、直線状に伸びるものから、数股に分岐するもの、地を這うタイプなどさまざまな形状があります。丸みを帯びたフォルムがスタイリッシュな「白雲閣」、不規則な凸凹が七福神の福禄寿に似ている「福禄寿」、無数の白い綿毛で覆われた「幻楽」などがあります。
■玉サボテン
コロンと丸く、可愛らしい見た目のサボテンです。柱サボテンが進化したもので、降水量が特に少なく極度に乾燥した地域にも対応できるよう、日光が当たる面積を小さくして水分をより多く蓄えることができるよう、球状になったものです。他のサボテンと比べても比較的病気になりにくく、トゲの短い「短毛丸」は綺麗なお花を咲かせるため人気の品種です。
■紐サボテン(森林サボテン)
柱サボテンの仲間で、細く長く伸びた茎が垂れさがるように育つのが特徴です。夜の間に良い香りの花を咲かせる「月下美人」や、赤・ピンク・黄・白などの花が咲くシャコバサボテン(クリスマスカクタス)、木や岩に着生し観葉植物として人気の高まっているヤドリギサボテン(リプサリス)などは、すべてこの分類のサボテンになります。
■コノハサボテン
サボテンの原種と言われる品種で、一見サボテンには見えない、葉を持つ通常の木のような形をしています。しかし葉の付け根や枝などにトゲと刺座があるため、れっきとしたサボテンの仲間です。サボテンの進化は「コノハサボテン」→「ウチワサボテン」→「柱サボテン」→「玉サボテン」の順だと言われています。白い花を咲かせ、ツツジにも見える「杢キリン」が有名です。
サボテンは暑さや寒さに強い?
サボテンが自生している砂漠や高地は日中と夜間の寒暖差が激しいため、最高気温40度ほどから、最低気温は5度前後まで耐えることができる丈夫なつくりをしています。暑さ寒さには強いですが、乾燥に適応して進化しているため、湿度の高い環境は苦手です。また氷点下には耐えられないので、基本的に5度を下回らない環境で育てましょう。
サボテンの季節別の管理ポイント(休眠期・生育停滞期)
ここからは、サボテンの季節ごとの管理ポイントをご紹介します。
サボテンの夏のお手入れ・管理
サボテンはしっかり日光に当てて育てる必要がありますが、実は日焼けで弱る場合があります。また真夏の暑い時間帯に水をやったあとに直射日光があたると、水が溜まる根の部分が高温かつ多湿になり、傷んでしまうケースも。夏場、特に梅雨明け後は直接太陽が当たらないように注意してください。昼と夜で気温差が少なく多湿な日本の夏は、サボテンの成長速度も落ちるので、水やりは様子を見ながら少なめにしましょう。
サボテンの冬のお手入れ・管理
先にも書いたとおり、サボテンは5度以下にならない環境に置きましょう。また冬場は霜に当てないように注意します。霜で凍ったあとは中身が腐ってぶよぶよの状態になってしまうので、寒冷地では冬期は室内に入れることをおすすめします。室内では日当たりのいい窓辺などに置き、日照をしっかり確保しましょう。またエアコンの風や加湿器の湿気が直接当たらないよう注意してください。
急激な寒さを感じるとストレスでサボテンが赤紫色に変色することがありますが、この場合は春には色が戻ることが多いです。
木質化とは?
サボテンや多肉植物の表面が茶色く変色し、木のように硬くなる現象を「木質化」もしくは「木化(もっか)」と言います。これは植物が枯れている状態とは区別されます。乾燥地帯で育つサボテンや多肉植物は、水分が奪われすぎないよう光合成できる部分をコンパクトにし、根元に近い部分を硬くすることで、他の部分に栄養を回して成長していけるように調整しているのです。長期間植え替えをしていないと木質化しやすくなります。「茶膜があがる」とも言われ、趣きがあるとしてこの状態を好む人もいます。
徒長とは?
日当たりが悪い場所でサボテンを育てていると、光が当たる方向を探してひょろひょろと伸びてしまうことがあります。 このように生育環境などが原因で本来とは異なる生長をしてしまった状態を「徒長(とちょう)」と呼びます。一旦徒長してしまうと元には戻りにくく形が悪くなるため、注意が必要です。
サボテンの育て方・お手入れ方法
それでは、サボテンの育て方やお手入れ方法を見ていきましょう。
①サボテンの設置場所
サボテンは日光を好むので、日当たりの良い場所に置きましょう。屋外がおすすめですが、直射日光が当たると「葉焼け」と呼ばれる日焼け状態になることがあるので注意してください。また風通しが悪いと病気や害虫が発生しやすくなるため、風通しのよい場所で管理します。
②サボテンの日当たり
とは言っても、日当たりが良いものの直接日光は当たらず、風通しは良いけれど雨は当たらない場所を探すのは難しいものです。家の東側など、午前中だけ直接日を当てることができる場所が良いでしょう。また家の南側に栽培棚を設置し、日差しが強くなる午後からの直射日光と雨を避けられる環境を作るのもおすすめです。
冬に冷え込んだり雪が降る地域では、室内に取り込んでください。前述のとおり、可能な限り日を当てることのできる窓辺で、乾かし気味に水やりをするのが徒長を避けるコツです。
③サボテンの水やり
サボテンには、よく成長する時期と、生育が停滞する時期があります。
まずサボテンの生育期は5~9月、真夏を除いた春の時期と、暑い時期が終わった秋です。この時期に大きく生長するため、しっかりと水を与えましょう。土の表面がしっかり乾いたタイミングで、鉢全体に行き渡り底の穴から流れ出るくらいたっぷりと水やりします。
また7~8月の夏場と、10~2月の冬場には生育が止まります。サボテンは暑さに強いですが、連日30度を超える環境では生育が緩やかになります。さらに乾燥して昼夜の寒暖差が激しい環境で生まれたため、夜間でも気温が高く多湿な日本の夏には元気がなくなります。気温が下がる秋以降は少しずつ生育が鈍くなり、冬になると完全に止まってしまいます。停滞期も休止期も根から水を吸い上げなくなるので、そこで水を与えると土の中が過湿になって根腐れの原因に。この時期の水やりは控えてください。
季節別の水のやり方
サボテンは気温によって必要とする水の量が変わります。日本では季節ごとに水やりの時間を変え、株に負担をかけないようにしましょう。おすすめの時間帯は下記です。
|
春(5月)
秋(9月) |
頻度:土が乾いたらすぐ
時間帯:午前中 |
|---|---|
| 夏(7~8月) |
頻度:土の表面が乾いてから2~3日後
時間帯:夕方~夜にかけて |
|
秋(10~11月)
冬の始まり(12月) |
頻度:2週間に1回
時間帯:昼間の気温が高いうち |
|
冬(1~2月)
初春(3~4月) |
頻度:3~4週間に1回
時間帯:昼間の気温が高いうち |
春と秋は比較的、昼夜の寒暖差もあり安定した気温です。ただし植物は光合成のため、朝日が昇る朝に葉の気孔を開き、呼吸と一緒に水を蒸発させます。このときにもっとも水を必要とするので、生育期である春と秋には午前中にたっぷり水をあげてください。
夏の昼間は高温になるので、ここで水をやると株が蒸れて傷む原因になります。夏場は日が落ちて涼しくなってから水やりをしましょう。
生長が止まる冬には水をやる必要はありませんが、例外的にまだ生育途中の小さいサボテンの場合、必要な水が足りなくなって枯れてしまう場合があります。気温が5度以上あり、特に乾燥がひどい場合は、様子を見ながら月1回ほど水やりをした方がよいことも。その際は、比較的気温の高い日を選んで昼間に行ってください。気温が低い時期に冷水を与えると根にダメージが出るので、15度程度のぬるま湯がおすすめです。
④サボテンの肥料
過酷な土地で生まれたサボテンは、あまり肥料を必要としません。成長期の秋と冬、月2~3回ほど、水やりの際に液状肥料を混ぜてあげると良いです。また植え替えの際は、元肥として土にひとつまみ程度の固形肥料を混ぜ込みます。どちらにしても、あげすぎは根腐れの原因になるため注意しましょう。
⑤サボテンの植え替え
サボテンが成長して最初に入っていた鉢ではサイズが小さくなったり、鉢底から根がはみ出したりしたとき。あるいは土の粒が崩れて細かくなり、水はけが悪くなってきたときは、植え替えを行ってください。目安は1~2年に1回程度ですが、輸送の際にこぼれないよう鉢の土がカチカチに固められた状態で販売されているサボテンもあり、その場合は購入後すぐに植え替えを行う必要があります。植え替えは株に負担をかけるので、生育期が始まる3月上旬~4月上旬にかけて行うとベストです。
植え替えの手順
植え替えの手順は、以下を参考にしてください。
- 水やりを止め、事前に土を乾燥させて根を引き抜きやすくしておく
- 新しい植木鉢の底に鉢底ネットと鉢底石を敷く
- 鉢底石の上に土を入れ、底から1/3くらいに届くまで盛る
- 古い鉢の側面を叩いて土を浮かせ、根を傷めないよう丁寧にサボテンを引き抜く
- 根を揉んで古い土をきれいに落とし、傷んだ根は取り除く
- 新しい鉢に根を広げながらサボテンを入れる
- 表面が縁から1cm程度低くなるまで土を足す
植え替え後は10日から2週間ほどは日陰に置き、さらにそこから5~10日ほど経過して、サボテンが新しい鉢に慣れてから水やりをします。
植え替えのポイント・注意点
植え換えの際はサボテンの根が切れてしまうことが多いですが、根の断面が完全に乾く前に水を与えると根腐れを起こします。そのため、前章でご紹介したように「サボテンを鉢から抜いたらすぐに新しい鉢に植え付けたうえで10日~2週間は水やりを控える」のですが、このほかに「サボテンを鉢から抜いた状態で1~2週間ほど乾かしておく」方法もあります。
この場合、サボテンを鉢から抜いて土を落としたら傷んだ根を取り、ザルなどに入れて1~2週間ほど直射日光や雨が当たらない場所に置いて、根を乾かしてください。いずれにしても、根の断面が乾き切らないうちの水気は厳禁です。
サボテンに適した土・鉢の選び方
ここからは、サボテンの栽培に適した土と鉢の選び方をご紹介します。
土の選び方
乾燥した環境で育つサボテンには、水はけと通気性の良い土が必要です。初心者の方は、市販されている多肉植物やサボテン専用の培養土を使うと安心です。既に肥料も含まれているので、特別な対応は必要ありません。
サボテン栽培に少し慣れてきたら、自分でブレンドして作ることもできます。その際におすすめの配合は「小粒の赤玉土6:腐葉土2:小粒の軽石もしくは川砂2」に固形肥料を少量足したものがおすすめです。
水はけが良いものがいいとはいえ、サボテンが元気に育つにはやはりある程度の保水力も必要。水をあげた後に少しずつ乾燥していくように配合します。
鉢の選び方
植木鉢の素材にはプラスチック・陶器・磁器・セメント・ガラス・金属などがあります。土が湿った状態が長く続くと根腐れを起こしやすいサボテンには、素焼きの陶器鉢(テラコッタ鉢)が向いています。が、鉢底から余分な水を排出できれば、磁器やプラスチック、金属などでも支障はありません。
サイズはサボテンの大きさに対してひと回り大きいものを選びましょう。あまり大きな鉢はそのぶん土が多くなり、土に含まれる水の量も増えるため、根が乾きにくく根腐れの可能性も高くなるため注意してください。
サボテンを増やすには?おすすめの増やし方

ここからは、サボテンを成長させて株を増やしていく、おすすめの増やし方をご説明します。
増やし方1:挿し木
サボテンに複数の株がついている場合、小さな株を切り取って別の鉢で育て、増やす方法です。サボテンは大元の株の上部や根元に小株ができることがあるので、そちらを利用します。株を切り取ったら、1週間ほど日陰で断面を乾燥させましょう。その後、新しい鉢に土を入れ、株の切り口がすべて埋まるように挿します。
増やし方2:接ぎ木
2種類のサボテンを組み合わせて大きくするやり方です。土台にするサボテンと大きくしたいサボテンを1つずつ用意し、土台部分とそこに繋げるパーツをそれぞれ水平に切り出します。両方の断面を隙間なく重ね合わせたら、マスキングテープや糸などで固定し、乾燥した日陰に置いてください。成長するに従ってぴったりとくっつき一体化します。
挿し木は、日本の高温多湿な環境に適応しにくく根腐れを起こしがちな種類を、より頑丈なサボテンに接ぎ木することで増やしたり、栽培しやすくすることができます。
増やし方3:種まき
サボテンは花が終わったあと、種から栽培することも可能です。株の生育状況が良いと花を咲かせるので、花が終わって実ができたら、中にある種を採取してまく方法です。
実から出した直後の種には発芽を抑制する物質が付いているので、砂などと一緒によく揉んで落としてしまいます。その後、ビニールポットに市販の種まき用の土や小粒の赤玉土などを入れて種をまきます。発芽の際は土が乾燥すると芽が出にくいので、ラップなどをかけておくと良いでしょう。芽が出たらラップを外して日当たりの良い場所に移動し、株として鉢に植え替えが可能なサイズになるまでビニールポットで育てましょう。
サボテンが枯れる原因は?
次は初心者が陥りやすい失敗、サボテンが枯れてしまう原因をご紹介します。
原因1:葉焼け(日焼け)
「葉焼け」は、直射日光が当たった部分の葉が変色して枯れてしまう現象を指します。サボテンは暑さに強いとはいえ、真夏の高温期に強い日差しに晒され続けると表面が傷んでしまう場合があります。特に日差しが強くなる午後からは、直射日光を避けられる場所に設置してください。
原因2:水のやりすぎ
土の中の水分が多すぎる状態が続くとサボテンの根は腐り始め、どんどん侵食されていきます。腐った根は必要な水分や養分を土から吸い上げられなくなるため、最終的には枯死に至ります。水やりは土がしっかり乾いたタイミングで行いましょう。また夏場に気温が30度を超えると土の中や根が蒸れやすくなり、冬場に気温10度を下回ると根が弱るため、これらの季節は水やりを控えてください。植え換えの際も、古い鉢から抜いた株を日陰で干して作業によって切れた根の断面が完全に乾いてから新しい鉢に植えるか、植え替え後に10日~1週間は水やりなしで土と根を乾かす必要があります。
原因3:鉢が大きすぎる
サボテンのサイズに対して鉢が大きく、そこに入っている土の量も多いと、土が乾燥するのに時間がかかり、やはり根腐れを起こす原因になります。鉢のサイズは適切なものを選び、水はけのよい土や通気性の良い素材の鉢を使いましょう。
適切な鉢のサイズは、サボテンの株の直径からひと回り程度大きなものです。初心者の方で土が乾燥する前に水をやってしまいがちな方は、乾きやすい素焼きのテラコッタ鉢がおすすめです。また、土に軽石を1~2割程度混ぜたり、鉢底石を多めに入れておくのも通気性を上げる方法です。
水切れ
根腐れを起こしやすいサボテンとはいえ、まったく水やりをしなくていいわけではありません。初心者の方に多い失敗は、水やりを控えるあまり、ついつい長期間忘れてしまうことです。特に夏場や生育期の春に水が足りない状態が続くと、さすがのサボテンも枯れてしまいます。サボテンの成長と健康には、日当たりと通気性の良い場所に置き、適度な水やりを欠かさないことが大切。季節によって頻度や水やりに適した時間帯も変わるので、心配な場合は予め携帯電話のカレンダーやリマインダーアプリに登録しておくとよいでしょう。
サボテンのかかりやすい病気・害虫対策
サボテンのかかりやすい病気・害虫
風通しが悪く多湿な環境に置かれているサボテンは、病気にかかったり害虫の被害に遭いやすくなります。特にサボテンがかかりやすいのは以下の3種類です。
■カイガラムシ・コナカイガラムシ・ワタムシ
トゲや皮の溝に付く害虫です。トゲの根元に白い塊があったら要注意。すぐに殺虫剤をまいて駆除し、歯ブラシなどで取り除いてください。コナカイガラムシは気温が下がると地中に潜るため、予防には春に植え替えを行い、土を入れ替えます。
■ネジラミ
根の周りに1~2mm程度の白い粉のようなものが付いていたら、ネジラミの可能性があります。ネジラミを発見した場合、掘り出したサボテンの土をすべて洗い落とし、薬剤を混ぜた水に浸けたあと乾燥。その後、鉢の土を清潔な土に交換して植え直します。サボテンの元気がないと感じたら根元を掘ってみると良いかもしれません。
■ハダニ
高温で乾燥した環境で発生しやすく、観葉植物でよく見られる害虫です。水に弱いので、予防には霧吹きを使って定期的にサボテン全体へ水をかけます。大量に発生した際は殺ダニ剤を使用しましょう。
これらの害虫はすぐに他のサボテンや観葉植物にも移ってしまうので、見つけたらすぐに対処することをおすすめします。
サボテンの病気の予防方法
サボテンは湿度の高い場所では病気にかかりやすくなります。サボテンがかかる可能性のある病気には以下のものがあります。
■立枯れ病
土に含まれる放線菌の一種で赤紫色になり、根元から茎に向かって腐敗。枯死に至る伝染性の病気です。
■黒斑病
黒い斑点が次第に全体に広がり、灰色のカビが生える病気です。
■くもの巣病
鉢が加湿になっている状態で、隣り合って密着した茎の付け根あたりに、白い綿毛状のクモの巣に似た菌糸が出る病気です。葉腐病とも呼ばれます。
■灰色カビ病
糸状菌と呼ばれるカビが原因で、葉の一部が灰色や褐色、黒色に変色して枯れたようになる病気です。次第に拡大して腐敗し、灰褐色のカビに覆われていきます。
菌が原因の病気には、殺菌剤は予防に有効です。病状が軽い場合は殺菌剤で元気になることもありますが、一度変色した部分は治らないため、病気になった部分から上部を切断して挿し木で植え替えましょう。
【初心者必見!】サボテンを育てる際の注意点
ここからは初心者の方が特に注意したい、サボテンを育てる際の注意点をご紹介します。
注意点1:直射日光を当てない
ここまで書いてきたように、サボテンは夏場に直射日光に当たると葉焼けを起こします。日当たりが良すぎる場所は避け、日差しが強くなる午後は置く場所を移しましょう。
注意点2:水やりは適切な回数で
土が乾ききらないうちに水をやると根腐れの原因になります。水やりは多すぎず少なすぎず、季節に合わせて適切な回数で行いましょう。
注意点3:根腐れを発見したらすぐに植え替える
根腐れを発見したらすぐに該当の箇所を切除し、新しい鉢と土を用意して植え替えます。指で株を揺らしたときにグラグラするようであれば根腐れを起こしている可能性があります。半年に1回程度、定期的にチェックしてみるとよいでしょう。
注意点4:置き場所に注意
日当たりと風通しの良い場所を好むサボテンは屋外で育てるのがおすすめですが、冬場は室内に移動させてください。慣れないうちによく起こしがちなミスは、日照を確保しようとして冬期に窓に近づけすぎて、冷気にやられてしまうことです。窓からは少し離れたところに置きましょう。サボテンの周りの空気が冷えすぎないことが大切なので、屋外では、ガラスやビニールケース、簡易温室などがあると安心です。
注意点5:エアコンの風を直接当てない
サボテンに限らず、エアコンの風が常に当たると植物は傷みやすくなります。夏場や冬場は特に気をつけてください。
観葉植物を選ぶなら日比谷花壇
日比谷花壇 では、サボテンをはじめとした 観葉植物 から、記念日やお祝いごとにぴったりのお花を使ったアレンジメントやブーケなど、幅広いアイテムを取り揃えています。
贈り物として選ぶ際には、お花のスタイル別や贈る目的別、予算別の検索が便利。最短翌日着のクイック配送や海外配送などのサービスもございます。またご自宅でも気軽にお花を楽しんでいただけるよう、その時期に見頃を迎える旬のお花を日比谷花壇のバイヤーがセレクトした 「バイヤーおまかせフレッシュ便」 、 自宅でお花を楽しむためのコツやアイディア などもご用意しています。また卒入学や就職・転職・転勤・お引越しなど、新しい生活を始める方向けには新居におすすめの観葉植物・グリーンやお花をご紹介していますので、 「新生活特集」 をご覧ください。
ぜひ、大切な人やご自身で楽しむのにぴったりのフラワーギフトを探してみてください。
まとめ
ここまで、特に初めてサボテンを育てたいと考えている初心者の方向けに、サボテンの歴史や由来・品種・特徴のほか、水やり・肥料・植え替えなど、基本的なお手入れの方法をご紹介しました。サボテンは育てるのが簡単で初心者向きだとよく言われますが、ポイントを押さえていないと意外と枯らしてしまうことも多い植物です。こちらの記事を参考に、ぜひお気に入りのサボテンを迎えて楽しんでください。