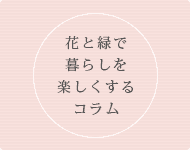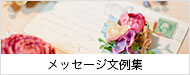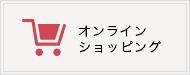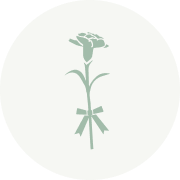最短で
07月31日
にお届けできます。
対象商品をさがす
美しい紫色をしたお花と他にはない芳しい香りを持ち、「ハーブの女王」と称されるほどの人気を集めるラベンダー。その香りにはリラックスや安眠だけでなく防虫・抗菌効果もあり、香水・化粧品のほかサシェやポプリなどにも活用されています。
今回は、そんなラベンダーを自宅で育ててみたい方向けに、品種・種類、栽培に適した地域といった基本情報から、育て方のポイント、お手入れ方法のコツをご紹介していきます。
ラベンダーとは?基本情報について

ラベンダーはシソ科ラヴァンドラ属(ラベンダー属)のハーブ。地中海沿岸を原産とし、主に4~7月に花を咲かせます。背丈が20~130cmほどの低木で、垂直に伸びた細い茎の先に紫色の小さい花を数多くつけるのが特徴。花・茎・葉はそれぞれ細かい毛で覆われていて、この毛の隙間から独特の芳香を持った精油を出します。ラベンダーの花は下から上に咲いていきますが、満開の状態がもっとも良い香りの精油を採ることができるそうです。
ラベンダーの品種・種類
ラベンダーの品種・種類にはいくつかの系統があり、品種によって香り方や耐暑性・耐寒性に違いが見られます。自分はどんなラベンダーを育ててみたいのか、購入する前に確認しておきましょう。
■イングリッシュラベンダー(アングスティフォリア系)
名前に「イングリッシュ(イギリスの)」とありますが、原産地はイギリスではありません。別名は「コモン(共通の)ラベンダー」「ファイン(良い)ラベンダー」で、数多いラベンダーの種のなかでも特に香りが良いことで知られる、もっともメジャーな品種です。
北海道で見ることができるのもこちらで、観賞用以外にも、ハーブやドライフラワー、ポプリ、香水など、さまざまな形で活用されています。マイナス15度までの耐寒性がありますが、日本の夏の高温多湿には弱く、北海道や東北などの寒冷地での栽培に適しています。
■フレンチラベンダー(ストエカス系)
パイナップルを思わせる形をしたユニークな姿のラベンダーです。小さな花が集まってできた花穂の先に、紫や白色の花びらのようなものが飛び出していますが、これは「苞葉(ほうよう)」と呼ばれ、花を守るために葉が変化したもの。ラベンダーの中では寒暖に強く丈夫で、花色も紫のほか、ピンク、ブルー、白と豊富。香りはやや弱いものの、開花時期が長いので観賞用やドライフラワー向きです。
寒さには弱いですが、反面、比較的暖かい地域でも耐えられるので、日本では栽培しやすい品種です。
■レースラベンダー(プテロストエカス系)
葉に入った切れ込みがレースのように見えることから名づけられました。観賞用に開発されたため、いわゆるラベンダーの香りはしません。その反面、ふっくらとした花穂と鮮やかな紫色が美しく、レースに似た葉とのバランスも優雅な品種です。寒さが特に苦手なので、寒冷地での栽培にはあまり向きません。
四季咲きのため、上手に育てると1年を通じて楽しむことができます。冬場は必ず霜を避けられる軒下か室内に入れて栽培してください。
■スパイクラベンダー(スパイカ系)
地中海西側からポルトガルにかけてが原産のラベンダーです。花色はやや灰色を帯びていて淡く、茎の先が複数に分かれて尖った穂のように花を付けます。開花時期も他のラベンダーより2ヶ月以上遅く、夏頃から初秋にかけてです。
いわゆる「ラベンダーの香り」として認識されているのはイングリッシュラベンダーの香りですが、こちらのスパイクラベンダーには甘さを感じさせる「酢酸リナリル」という成分が含まれておらず、比べると男性的ですっきりとした強い芳香を持つため、防虫剤にもよく使用されています。耐暑性が強く、日当たり・風通しの良い乾燥した場所を好む品種です。
■ラバンディン系
香りの良いイングリッシュラベンダーと暑さに強いスパイクラベンダーを掛け合わせた交雑種。背が高くやや長めの花穂を持ち、耐暑性・耐寒性が強いのが特徴です。
ラベンダーのなかでは育てやすく、初心者のほか、関東以南の温かい地域にも向いています。ラバンディン系でも特に「グロッソ」という品種は大株で、香りも良いので人気があります。
■デンタータ系
フレンチラベンダー(ストエカス系)から派生した品種で1mほどになり、お花以外に葉の緑色も美しいことから、切り花として人気があります。開花時期は基本的に春から夏にかけてですが、株が安定して大きくなれば、高温期と低温期を除いて四季咲きとしても楽しめます。
暑さと乾燥に強く、ラベンダー栽培では1つの関門とされている夏越しも比較的簡単にできますが、反面、寒さと梅雨の時期の多湿にはとても弱い品種で、やや上級者向けです。
ラベンダー栽培に適した地域
寒さに強く、日本の夏の暑さと湿気に弱いイングリッシュラベンダーは、北海道や東北といった寒冷地での栽培が向いています。夏場に高温となる関東以南では、暑さに強く育てやすいラバンディン系やフレンチラベンダー(ストエカス系)の品種が適しています。レースラベンダー(プテロストエカス系)、デンタータ系も温暖な地域向きですが、こちらは特に寒さに弱く扱いに注意が必要なので、ラベンダーの栽培に慣れた上級者向きと言えます。
ラベンダーの育て方とポイント
ラベンダーの栽培環境・場所について
ラベンダーは日当たりと風通しの良い場所を好むお花。日照が不十分だとそれだけで枯れてしまうことがあるほどです。また高温多湿な環境も苦手です。
室内栽培では日当たりの良い窓辺がおすすめですが、開花期間中は最低気温が10度以上になるように注意しましょう。日中は20度以上を保つのが花持ちを良くする秘訣ですが、25度を超える日が続くと、今度は徒長(植物の茎や枝が必要以上に伸びて形が乱れること)の原因となり、短命になってしまいます。
屋外栽培の場合は、夜間に霜に当たらない環境で管理します。庭などに地植えする場合、日陰の状態が半日以上続く場所は避けてください。また直射日光や夏に強い西日が当たる場所、湿気がこもる場所もNGです。冬場の日照が良く、夏場の日差しを遮る落葉樹の側などが良いでしょう。
鉢植えの場合、市販されているラベンダー用培養土やハーブ用の土を使用するのがおすすめ。地植えするのであれば、土壌改良をして水はけを良くしておきましょう。元の土に対して堆肥や腐葉土を2割、「パーライト」や小粒の「日向土」と呼ばれる軽石系を1割になるよう混ぜます。またラベンダーはアルカリ性の土を好みますが、日本の土は酸性寄りなので、苦土石灰や有機石灰・もみ殻くん炭などをさらに加えておきます。
ラベンダーの植え付けについて
ラベンダーの植え付けに適した時期は、主に3~4月頃の春か初秋です。特に関東以南の地域では、暑さが収まり冷え込みも始まっていない秋の早いうちに植え付け、しっかり根を張らせてから開花時期の春を迎えるようにしてください。イングリッシュラベンダー(アングスティフォリア系)やラバンディン系の場合、春に植え付けると苦手な夏場にあまり生長できず、夏越しが難しくなるので秋に植え付けましょう。
またラベンダーは過湿を嫌うため、植え付けは晴れた日が続いているタイミングで行ってください。当日に雨が降っていたり、翌日に高確率で降雨があるとわかっているときは避けた方が無難です。
鉢植えの場合、大きすぎる鉢は加湿の原因となるので、5~6号サイズの鉢に1株を植えます。水はけや通気性の向上のために鉢底石を敷くのを忘れずに。鉢の土は少々高めに盛ってください。
庭植えの場合は、水はけを良くするため予め地中深くまで耕しておき、鉢植えと同様に土を高めに盛って高植えにします。
ラベンダーの植え替えについて
ポットに入れて売られているラベンダーの苗を購入したらすぐに、もしくは、育てているラベンダーが大きくなってきたら植え替えを行ってください。
鉢植えの場合は、これまでよりもひと回り大きな鉢を用意し、鉢底石を底に敷きます。植え付けの際に使った市販の培養土か、ラベンダー用に調合した土(赤玉土3割、パーライト・バーミキュライト・小粒日向土1割、苦土石灰・有機石灰・もみ殻くん炭1割)を高めに盛って入れ、緩効性肥料も加えましょう。ポットや鉢からラベンダーの株を取り出したら、根を少しほぐしてから土に入れます。
地植えの場合、株よりも1~2回り大きな穴を掘り、植え付け時と同様の堆肥・腐葉土2割、パーライト・小粒日向土1割、苦土石灰・もみ殻くん炭1割ほどを元の土と混ぜて、高盛りにして植えこみます。
ラベンダーの水やりについて
ラベンダーは過湿を嫌うお花です。従って鉢植えの場合、土の表面が乾いて葉が柔らかく下がってきたタイミングで水やりを行ってください。このときは鉢底から水が流れ出るほど、たっぷりと与えます。表面の土がまだ湿っているうちに水を与え続けていると、根腐れを起こして枯れてしまうこともあるため、必ず水やりの前に鉢土の状態をチェックする習慣をつけるのがコツです。特に夏場は水が足りなさ過ぎても枯れてしまうため、水切れを起こさないように注意しましょう。
地植えの場合、植え付け直後から1週間ほどはまだ根が張り切っていない可能性があるので、土が完全に乾いているようなら水やりしてください。その後、きちんと根づいてからは雨に任せます。人為的に水やりをする必要はほぼ、ありません。夏場の猛暑や晴天続きで土がカラカラに乾燥しているときのみ、適宜水を与えます。
どちらの場合も、水やりをする時間は朝がおすすめです。特に夏場は昼から午後にかけて高温になり、熱せられた水が根を傷めてしまうので、なるべく早朝に行うよう心がけてください。
ラベンダーの肥料について
ラベンダーは肥料を与えすぎると弱ってしまうため、適量を与えることが大切です。春もしくは秋に植え付けや植え替えする場合は、土に緩効性肥料を混ぜ込みましょう。
追肥としては、成長期を迎える3~4月に1回と、開花を終えて再度成長する9月頃にもう1度、緩効性肥料を施します。肥料は草花用として市販されている一般的なもので問題ありません。
注意点としては、梅雨が始まる前には必ず肥料をストップすること。ラベンダーが苦手とする夏の時期に肥料が残っていると傷みやすくなるためです。同様に、寒さが厳しい冬の時期も施肥はNGです。
ラベンダーの日当たりについて
既に書いたとおり、ラベンダーは日当たりが良く風通しの良い場所を好み、湿気や蒸し暑さを嫌います。鉢の置き場所・植える場所は日当たり・風通しが良い場所を選び、水はけの良い土に植えてください。
鉢植えの場合、西日が厳しい時間帯には日陰に異動させるか、日よけシートや寒冷紗を用意して張りましょう。また地面からの照り返しの予防として、市販のフラワースタンドや棚など高い位置に置くのもおすすめです。
地植えの場合、株同士の間隔は50~60cm程度にして植えていきます。日当たりが良ければ、夏場の直射を避けられる軒下や、冬場の日照が確保できる落葉樹の側なども適しています。ただし、寒さにことに弱いレースラベンダー(プテロストエカス系)やデンタータ系は、充分な防寒対策を行うために、関東以南の比較的温暖な地域でも鉢植えにした方が良いでしょう。
ラベンダーのお手入れ方法とコツ
ラベンダーの増やし方
ラベンダーは3年ほど育てると、枯れやすく新芽もつきにくくなってきます。そのため、挿し木(挿し芽)で株を新しく増やしていきましょう。
挿し木に適した時期は、生長が盛んな春です。「天芽」と呼ばれる枝先を10cmほど切り、「挿し穂」と呼ばれる土台にします。切り口は水に浸け、1時間ほど水を吸わせてください。その後、挿し木用に用意した土に穴を掘って切り口を挿し、穴を埋めます。このとき、土は必ず雑菌が少ない清潔な新しい土を使用してください。
土に挿したあとは、1ヶ月ほど日陰に置いて管理します。土が乾かないよう、この間は水やりをこまめに行い、1ヶ月程度で発根するので、鉢や花壇、庭などに植え替えます。植え替え後は通常の苗と同様に育て問題ありません。
挿し木の時期は花後の成長期である秋でもOKですが、春の方が若い苗は夏越ししやすようです。
ラベンダーの剪定について
ラベンダーを育てていくうえで、剪定は欠かせない作業です。春の開花時期が終わったら、株の蒸れを防ぐため、梅雨を迎える前に剪定します。またお花の部分を切除することで種ができなくなるため、株にかかる負担を軽減することもできます。
花後の剪定を行うには、まず茎についている新芽を探し、その少し上をカットします。さらに枝の混雑した部分や、土や泥はねがつきやすい下の方の枝もカットしてしまいましょう。
花後ではなく、育てたラベンダーを切り花として飾りたい場合に剪定を行うこともあります。この場合は、お花が終盤になると花がらが落ちやすくなるため、開花してすぐに行うことをおすすめします。またドライフラワーにするのであれば、雨の日を避けてお天気が良い日に行ってください。
栽培を初めて2~3年ほど経つと、株が大きくなる一方で根元が木質化(茎が茶色に変色して木のように硬くなること)し、下の方に葉がなくなってくるため、メンテナンスとしての剪定が必要です。この剪定を「強剪定(更新剪定)」と呼びます。これを行わないと古いままの枝が残って新芽が付きくくなったり、枝が混みあって風通しが悪くなり、株が痛む原因になります。強剪定を行うのに適した時期は、秋から春先頃。花芽をカットしてしまわないように新芽がつく時期は避けてください。花の咲いている茎を下へ辿っていくと新芽が見つかるので、この芽の上あたりでカットしましょう。古い枝や太すぎる枝なども間引いて剪定し、最後は鉢の大きさに合わせて、横から見たときにドーム型になるよう、枝の長さを全体的に整えていきます。強剪定は毎年行ってください。
ラベンダーの夏越し・冬越しについて
ラベンダーを枯らしてしまうのは夏と冬が特に多く、夏越しと冬越しがポイントになります。
夏場はどうしても株が弱りやすいので、ラベンダーが苦手とする過湿に注意しましょう。特に梅雨の時期は、鉢植えは雨が当たらない場所へ移動させてください。ただし水切れを起こすと枯れてしまうので、鉢土の表面がしっかり乾いたことを確認してから、鉢底から溢れるくらいたっぷりと水やりをするのを忘れずに。
冬場に注意が必要なのは霜です。防霜には、市販のマルチング剤や敷き藁を使って土を覆うと良いでしょう。寒さに弱い品種は地植えにせず、予め鉢植えにしておき、冬のあいだは室内で管理してください。日照不足になりやすいので日当たりの良い窓際に置き、屋内でも気温の下がる夜は暖かい場所へ移動させます。
ラベンダーのかかりやすい病気・害虫
ラベンダーの気を付けたい病気
ラベンダーはあまり病気の被害を受けない植物です。
ただし、高温多湿な環境で蒸れると葉が灰褐色に変色し、萎れて落ちてしまいます。気温が上がってきた初夏、成長期の秋や春先には切り戻し(花が終わったあとや生育が旺盛で形が乱れてきたときに、すべての枝が鉢の周りに沿ってはみ出さないよう、バッサリ切り落とすこと)を行って風通しを良くしてあげましょう。それ以外にも、枝が混み合ってきたら適宜剪定を行います。
ラベンダーの気を付けたい害虫
ラベンダーはそれ自体に防虫効果があるため、あまり害虫の被害を受けません。ただし春先に以下の害虫がつくことが稀にありますので、その際は対策を取ってください。
■アブラムシ
新芽や茎などに多くつく代表的な害虫です。葉から栄養を吸って株を弱らせるほか、ウイルス病などの病気の原因になる場合もあります。アブラムシはすぐに増えてしまうので、見つけ次第取り除き、薬剤を散布して予防してください。
■ハダニ
葉の裏側などに付く虫で、葉が掠れたような色に変色することで発覚する場合が多いです。ハダニは温度が高く乾燥した環境で発生するため、風通しの良い場所に置き、霧吹きなどで葉にこまめに水を与えて防ぎます。殺ダニ剤などの薬剤も有効です。
ラベンダーの歴史や由来
ラベンダーはエジプトからギリシャ・ローマ、アラビア、ヨーロッパなど幅広い地域で、古来からハーブとして薬や調理に利用されるとともに、その香りも活用されてきました。ハーブとは、「生活に役立つ香りのある植物」の総称。植物のパーツのうち葉・茎・花を利用するものを「ハーブ」、根・種・実を使うものを「スパイス」とと呼んで区別することもあります。そのなかでも、ラベンダーは「ハーブの女王」という異名を持つほどに世界的に長く活用されてきた歴史を持ちます。
ただし、ラベンダーは長く野生種を採取して使われてきていて、本格的に栽培が始まったのは1930年代とも言われています。日本では1937年に香料として輸入されたのが始まりだと言われますが、幕末頃には既に一部で精油が輸入され、栽培も行われていたとも伝えられます。香料の原料として本格的に栽培が始まったのは昭和になってからで、1970年台には北海道富良野地方を中心にピークを迎えました。その後は合成香料の台頭で衰退しますが、現在でも富良野のラベンダー畑は人気の観光地となっています。
ラベンダーの語源は、ラテン語で「洗う」という意味の「lavare」です。これはイエス・キリストの産着を、聖母マリアがラベンダーの香水を使って洗濯したという言い伝えが由来だとされます。また古代ローマでは、沐浴や選択にラベンダーの花を入れたり、ラベンダーの精油で傷口で洗っていたとも言われ、このことがラベンダーの名前の由来であるという説も有力です。
ラベンダーの育て方に関するよくある質問
Q&A①:冬場にラベンダーを室内に入れたら形が悪くなった。何が原因ですか?
ラベンダーは極端な寒さ暑さに弱い品種です。冬場と夏場は生長が止まるので、基本的に肥料を必要としません。過分な肥料は根を傷める原因になるので、冬と夏には肥料を与えないようにしてください。この間、どうしても形は悪くなりますが、春になって屋外に出す際に切り戻したうえで追肥を行えば、また新たに芽吹いて形も整うようになるでしょう。
Q&A②:ラベンダーを植え替えたら枯れてしまった。理由は何が考えられますか?
植え替えは必要があって行うものですが、植物にはどうしても負担がかかります。考えられる主な理由は、①植え替えに適さない時期に行った、②プランターや地面に植える際に株同士の距離が近すぎた、③ポットや鉢から取り出す際に根を大きく傷つけた、などです。
ラベンダーの植え付けに適した時期は、主に3~4月頃の春か初秋です。関東以南の地域に住んでいたり、暑さに弱い品種の場合は秋に植え付けましょう。また、株同士は50~60cmほどの間隔を空けて植えてください。植え替えの際は葉や茎が込み合わないように刈り込んで、根は傷つけないよう丁寧に取り出し、ほぐしてから土に入れましょう。
ラベンダーの花を選ぶなら日比谷花壇
日比谷花壇 では、ラベンダーをはじめとした多くの鉢植えやアレンジメント、花束などを幅広く取り揃えています。
記念日やお祝いごとの贈り物として選ぶ際には、お花のスタイル別や贈る目的別、予算別の検索が便利。最短翌日着のクイック配送や海外配送などのサービスもございます。
またご自宅でも気軽にお花を楽しんでいただけるよう、その時期に見頃を迎える旬のお花を日比谷花壇のバイヤーがセレクトした 「バイヤーおまかせフレッシュ便」 、 自宅でお花を楽しむためのコツやアイディア などもご用意しています。
ぜひ、大切な人やご自身で楽しむのにぴったりのフラワーギフトを探してみてください。
まとめ
ここまで、これからラベンダーを育てたいと考えている方向けに、ラベンダーの特徴や主な品種・種類、栽培に適した場所といった基本情報から、育て方のポイント、お手入れのコツなどをご紹介してきました。
1度嗅いだら忘れられない甘くすっきりした香りと、生花でもドライフラワーでも美しい紫色のお花が魅力的なラベンダーは、手元で育てるとより奥深い魅力を味わうことができます。同時に品種ごとに特性が異なるため、自分の住む地域にあった品種を選ぶことが重要です。こちらの記事を参考に、ぜひお住まいの地域に合ったラベンダーを迎えて育ててみてください。