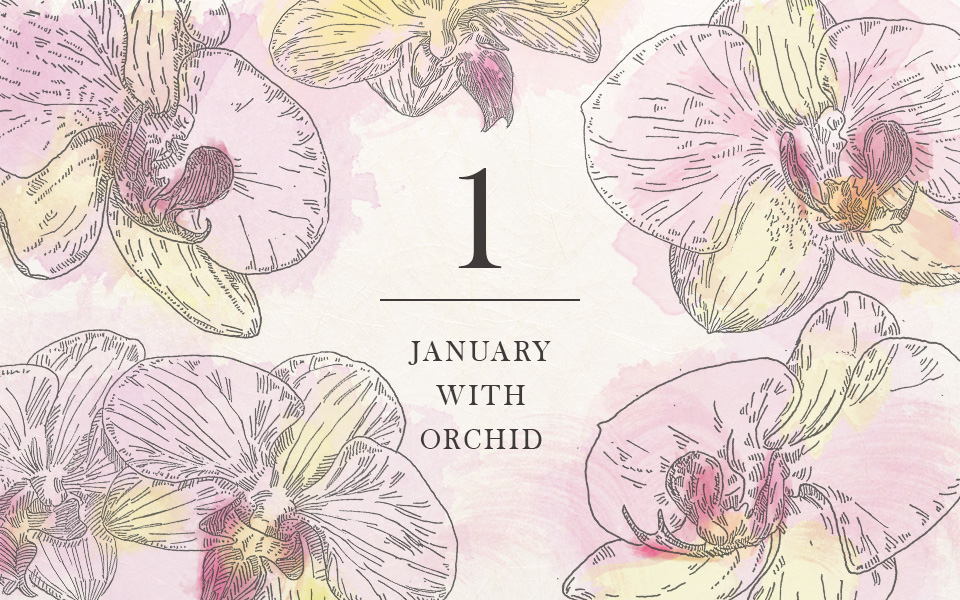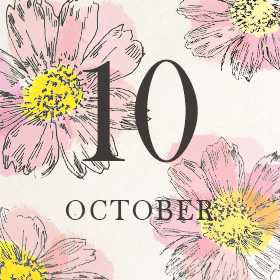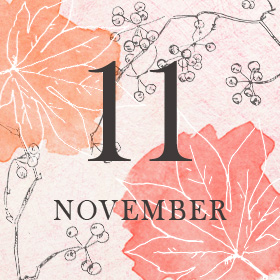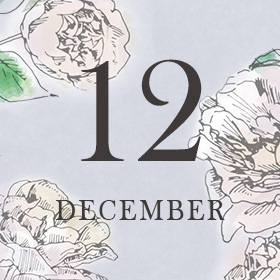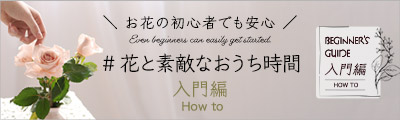睦月を「コチョウラン」で楽しむ
ENJOY JANUARY WITH ORCHID
年が明け、新鮮な気持ちで新しい年を迎える睦月。
旬のお花とともに季節を楽しみましょう。
-

- 寒さが極まるやや手前のころのこと。この時期を「寒」とするため、「寒の入り」を迎えたともいいます。
-

- 一年で最も寒さが厳しいころのこと。冬の最後の節気であり、次第に春に向かう時期でもあります。
五節句の一つで、一年の豊作と無病息災を願い七草粥を食べるのが習わしです。「七草の節句」とも呼ばれています。
元々は中国で1月7日に無病息災を願い、7種類の野菜が入った食べ物を食す風習があり、これが日本に伝わってきました。
日本でも年の初めに若菜を摘んで食べるという「若菜摘み」という風習があり、この二つが合わさったものが現在の七草粥になったといわれています。

優雅な花姿を長く楽しめる「コチョウラン」
お祝い花として人気が高く、「胡蝶蘭」という名の通り蝶が舞っているような美しい花姿が特徴です。
もともと熱帯地域で自生していた花で約200年前に発見され、日本に伝わってきたのは約100年ほど前といわれています。
当時は大変高価で庶民には手の届かない「高嶺の花」でした。
しかしながら、時代とともに栽培技術が向上し年間を通して栽培できるようになったことや、「花もちのよさ」「香り・花粉が少ない」ことが好まれて庶民にも徐々に親しまれるようになりました。
花言葉も「幸福が飛んでくる」と大変縁起が良く、今やお祝いの花として欠かせない存在です。
鉢植えが一般的ですが、切り花にしても花もちが良く、長く花を楽しめるのでご自宅を彩る花としてもおすすめです。

仲睦まじく新年を迎える1月
年末に家の中を掃き清め、しめ飾りや門松などを飾って歳神様をお迎えするお正月。
古来より「歳神様」はその年の五穀豊穣や家内安全をもたらしてくれると信じられていました。
しめ飾りや門松は、歳神様への目印。現在の「門松」は竹の存在が目立っていますが、その名の通り本来の主役は松。
常緑樹で古来から縁起が良いといわれており、神様を迎えるのにふさわしいと考えられていました。
地域差がありますが、1月7日頃までを「松の内」というのは門松を飾っておく期間だからです。
1月の和名「睦月」の由来は諸説ありますが、一説にはお正月に家族が集まり仲睦まじく過ごす様子から来ているといわれています。
お正月飾りに新しい年の願いを込め、一家団欒で賑やかに過ごしましょう。
- 季節のお花と合わせたお菓子をご紹介
-

-
松の木肌を渋皮栗で見立てて、立派な老松を表現された和菓子「老松」、冬でも青々とした竹の生命力を表現された和菓子「若竹」、本紅色を特徴とした和菓子「紅梅」と、お正月の時期ならではのおめでたい「松竹梅」で合わせました。
撮影協力:岡埜栄泉総本家 いろがみ wagashi.irogami