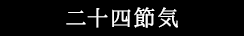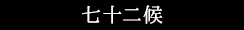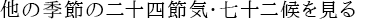日本人は昔から季節感を大切にして暮らしの中に取り入れてきました。
節分を基準に一年を24等分に分け、春・夏・秋・冬などの名称を付けたのが
「二十四節気」
です。
そして、その二十四節気の節気ひとつひとつをさらに三区分し、季節の風物を言葉で表現したものが
「七十二候」
です。
あなたも、日々の暮らしに、四季の移ろいを取り入れて、心のゆとりを感じてみませんか?

白露とは、大気が冷えてきて露を結ぶころのこと。
ようやく残暑が引き、本格的な秋の訪れを感じるようになります。
-
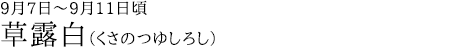
-
草に降りた露が白く光って見えるころ。
朝夕の涼しさが、くっきりと際立ってきます。
夜は、空気が透明になって、月の明かりが鮮やかさを増します。 -

-
鶺鴒(せきれい)が鳴き始めるころ。鶺鴒は水辺に多く生息する野鳥。
チチチチチ・・・という鳴き声が印象的な鳥です。 -

-
つばめが子育てを終えて、南に帰るころ。
春先に訪れた渡り鳥としばしのお別れです。
そろそろ長袖のほうが過ごしやすくなってくる時期です。

秋分とは、春分と同じく昼夜の長さが同じになる日。
これから次第に日が短くなり、秋が深まっていきます。
-
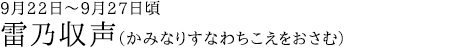
-
夕立に伴う雷が鳴りをひそめるころ。
入道雲から鰯雲へ、雲の形も様変わり。秋の空が晴れ渡ります。 -
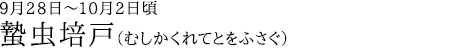
-
虫たちはこのころ、早くも冬ごもりの支度に入ります。
幼虫がさなぎになったり、卵を産んだり、土にもぐって春の訪れを待つのがこの季節です。 -
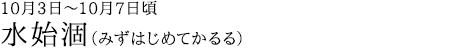
-
川の水が涸れる、という意味ではなく、田から水を抜き、稲刈りに取りかかるころのことです。
たわわに実った稲穂はまさに収穫の時、秋まっただ中です。