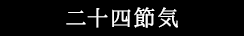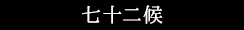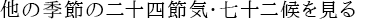日本人は昔から季節感を大切にして暮らしの中に取り入れてきました。
節分を基準に一年を24等分に分け、春・夏・秋・冬などの名称を付けたのが
「二十四節気」
です。
そして、その二十四節気の節気ひとつひとつをさらに三区分し、季節の風物を言葉で表現したものが
「七十二候」
です。
あなたも、日々の暮らしに、四季の移ろいを取り入れて、心のゆとりを感じてみませんか?

本格的な冬が到来し、雪が降り出すころのこと。
降雪地方では、雪の重みで木が折れないように雪吊りをします。
-
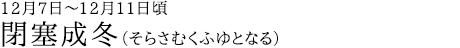
- 天地の陽気がふさがり、真冬が訪れるころ。今にも雪が降り出しそうな日が増えてきます。重たい灰色の雲におおわれた空は雪曇(ゆきぐもり)と呼ばれます。
-
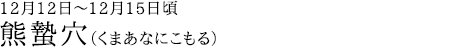
- 熊が穴に入って冬ごもりするころ。冬の間に、子どもを生み育てる雌もいるそうです。他にも蛙やこうもり、シマリスなど、冬眠をする動物が穴にこもり始めます。
-
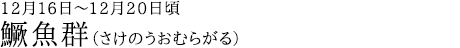
- 鮭が群れをなして川を遡るころ。冬を迎えると、海で育った鮭が、産卵のため一気に川を遡上します。北国の冬の風物詩ともいえる鮭の里帰りの光景が見られます。
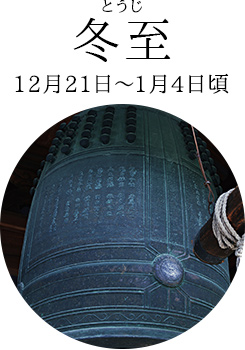
一年で最も昼が短く、夜が長いころのこと。
この時期を境に日が伸びていくので、古代には冬至が一年のはじまりでした。
-

- 靫草(うつぼぐさ)の芽が出てくるころ。「夏枯草」「乃東」とも呼ばれ、冬至の頃に芽を出して、夏至の頃に枯れることからこの名がつきました。
-
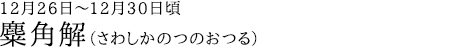
- 鹿が角を落とすころ。この「鹿」は日本鹿ではなく、ムースやエルク等、西欧の大型の鹿を指すと言われています。古来の日本人が異国へのロマンをはせた名残かもしれませんね。
-
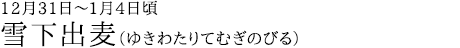
- 降り積もる雪の下で、麦が芽を出すころ。地中や、冬木立の枝先で植物は芽吹く力を育みます。重い雪の中で暖かい春をじっと待っているのは、人間も植物も同じ、ということです。