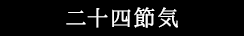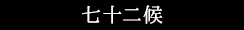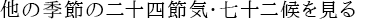日本人は昔から季節感を大切にして暮らしの中に取り入れてきました。
節分を基準に一年を24等分に分け、春・夏・秋・冬などの名称を付けたのが
「二十四節気」
です。
そして、その二十四節気の節気ひとつひとつをさらに三区分し、季節の風物を言葉で表現したものが
「七十二候」
です。
あなたも、日々の暮らしに、四季の移ろいを取り入れて、心のゆとりを感じてみませんか?

寒露とは、露が冷たく感じられてくるころのこと。
空気が澄み、夜空に月が冴え冴えと映える季節です。
-

-
雁が北から渡ってくるころ。
その年初めて訪れる雁を、初雁(はつかり)といいます。
隊列を組んで群れでやってくる雁の姿は秋の趣があります。 -
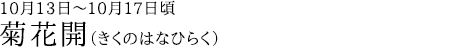
-
菊の花が咲き始めるころ。
菊は初め薬草として、奈良時代に中国から伝わったと言われています。 -
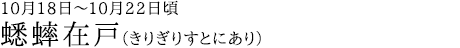
- きりぎりすが、戸口で鳴くころ。山野に出かけて虫の声を楽しむことを虫聞きと呼び、平安時代から親しまれています。

霜降とは、朝夕にぐっと冷え込み、霜が降りるころのこと。
山々の紅葉が見頃を迎え、晩秋の雰囲気が色濃くなってきます。
-
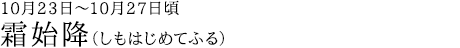
-
霜が初めて降りるころ。足元から冷えを感じるようになる時期です。
この日から立冬までに吹く北風を木枯らしと呼びます。 -
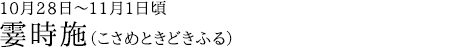
- 時雨が降るようになるころ。古くは芭蕉も歌に詠んだ、秋の初時雨は野山の生き物や人々にとっての冬支度を始める合図です。
-
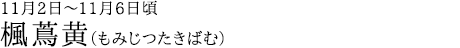
-
紅葉(もみじ)や蔦が色づくころ。
草木が黄や紅に染まることを、もみつといったのが語源だそうです。