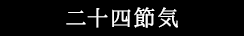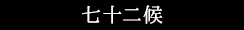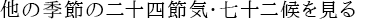日本人は昔から季節感を大切にして暮らしの中に取り入れてきました。
節分を基準に一年を24等分に分け、春・夏・秋・冬などの名称を付けたのが
「二十四節気」
です。
そして、その二十四節気の節気ひとつひとつをさらに三区分し、季節の風物を言葉で表現したものが
「七十二候」
です。
あなたも、日々の暮らしに、四季の移ろいを取り入れて、心のゆとりを感じてみませんか?

万物が清々しく、明らかな美しさをあらわすころ。
空には、南から帰ってきたツバメの姿がよく見られます。
-

- 冬の間、暖かな東南アジアで過ごしていたツバメが日本に帰ってくるころ。ツバメが巣をかけた家は栄えるといわれています。去年作られた巣を見ながら、帰りを待ちわびている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
-
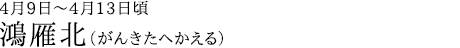
- 雁(がん)が北へ帰るころ。鳥の群れが羽ばたく羽音は、風の鳴る音に聞こえることから「鳥風(とりかぜ)」と呼ばれ、春先の北国に広がる曇り空を「鳥曇(とりぐもり)」というそうです。
-
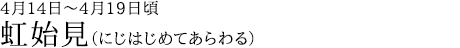
- 春の雨上がり、空に虹がかかり始めるころ。これから夏に向けて、虹を見る機会も増え始める季節になります。虹は空の水滴が反射してできるものですが、春の虹は特に淡く、繊細な雰囲気です。

穀雨とは、たくさんの穀物をうるおす雨が降るころのこと。この季節の終わりには、いよいよ夏のはじまりを告げる八十八夜が訪れます。
-
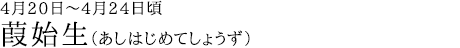
- 水辺の植物「葦」にも春がやってきて、芽を吹きはじめるころ。川辺から顔を出す若芽の先が、とんがっていて牙に見えることから「葦牙(あしかび)」といい、季語では「葦の角(あしのつの)」とも呼ばれています。
-
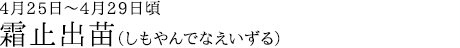
- 霜のおおいがとれて、健やかに苗が育つころ。種籾が芽吹き、すくすくと伸びていきますが、先駆けて旬をむかえるのは薬草の「ヨモギ」です。すりつぶしたヨモギがたっぷりと入っている「草餅」は栄養満点。
-
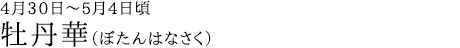
- 華やかに牡丹の花が咲きだすころ。立春から数えて八十八日目の夜を「八十八夜」と呼び、もうすぐ初夏を迎える時期となります。「米」という文字が八と十と八を重ねて出来上がることから、縁起のいい「農の吉日」とされています。