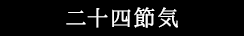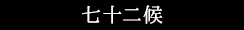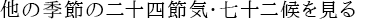日本人は昔から季節感を大切にして暮らしの中に取り入れてきました。
節分を基準に一年を24等分に分け、春・夏・秋・冬などの名称を付けたのが
「二十四節気」
です。
そして、その二十四節気の節気ひとつひとつをさらに三区分し、季節の風物を言葉で表現したものが
「七十二候」
です。
あなたも、日々の暮らしに、四季の移ろいを取り入れて、心のゆとりを感じてみませんか?

小暑とは、梅雨が明けて本格的な夏になるころのこと。
この小暑から立秋になるまでが、暑中見舞いの時期です。
-
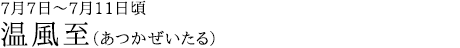
-
夏の風が熱気を運んでくるころ。
梅雨明け頃に吹く風を白南風(しろはえ)と呼ぶようです。 -
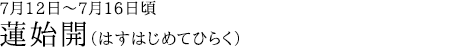
-
蓮の花が咲き始めるころ。
夜明けとともに水面に綺麗な花を咲かせます。 -
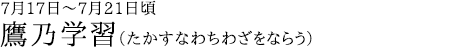
-
鷹のひなが、飛び方をおぼえるころ。
巣立ちし、獲物を捕らえ、一人前になっていきます。
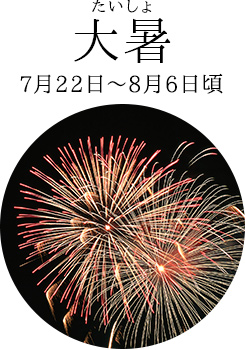
大暑とはもっとも暑い真夏のころのこと。
土用のうなぎ、花火と風物詩が目白押しです。
-
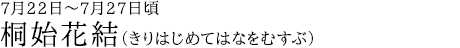
-
桐が実を結び始めるころ。
日本の暮らしの中で、桐は家具として役立ってきました。 -
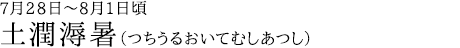
-
むわっと熱気がまとわりつく蒸し暑いころ。
打ち水や夕涼みなど、暑さをしのぐひとときを過ごしましょう。 -
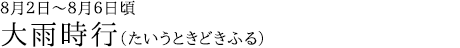
-
夏の雨が時に激しく降るころ。
青空に入道雲が広がるのもこの時期です。