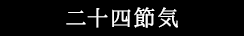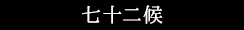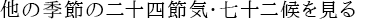日本人は昔から季節感を大切にして暮らしの中に取り入れてきました。
節分を基準に一年を24等分に分け、春・夏・秋・冬などの名称を付けたのが
「二十四節気」
です。
そして、その二十四節気の節気ひとつひとつをさらに三区分し、季節の風物を言葉で表現したものが
「七十二候」
です。
あなたも、日々の暮らしに、四季の移ろいを取り入れて、心のゆとりを感じてみませんか?

降りそそぐ太陽の光に、あたたかな春の兆しが表れてくるころのこと。
この季節に初めて吹く、南寄りの強い風を「春一番」といいます。
-
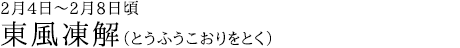
- 温かい春風が吹いて、川の氷が解けだすころ。東ではなく温かいのは南の風では?と思うかもしれませんが、それは七十二候が中国から渡ってきた暦であることの名残です。中国の陰陽五行という思想で、春は東を司ることから、「東風」と呼ぶそうです。
-
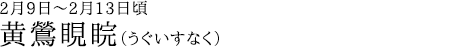
- 春の訪れを告げる鶯が、美しい鳴き声を響かせるころ。鶯を「春告鳥(はるつげどり)」というように「春告魚(はるつげうお)」といわれるニシンがおいしい季節です。かつては梅の咲く季節「梅花乃芳(うめのはなかんばし)」とも呼ばれていました。
-
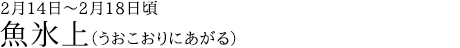
- 温かくなり川の氷が割れ、魚が跳ね上がるころ。各地では次第に「渓流釣り」が解禁となり、旬のイワナやヤマメ、アマゴなどを釣ることができます。岐阜県揖斐郡では2月18日に豊年祈願祭「谷汲踊り(たにぐみおどり)」が行われます。鳳凰の羽をかたどった4mもの鮮やかな「シナイ」は風物詩です。
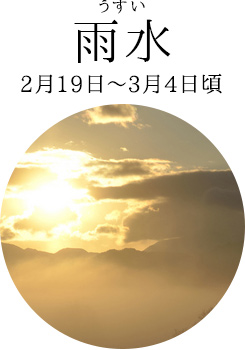
降る雪が雨へと変わり、氷が解けだすころのこと。
昔から草木が芽生えはじめると、農耕の準備をはじめる目安にされてきました。
-
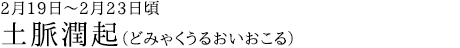
- 早春らしい暖かな雨が降り注ぎ、大地がうるおい目覚めるころ。水分を吸った土の香りが心地よく漂いはじめます。花々の香りよりも先に春の訪れを知らせ、春キャベツなどの作物に旬を迎えさせるなど、土にとっては大忙しの季節です。
-
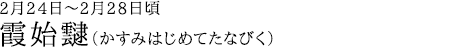
- 霧(きり)や靄(もや)で山野の情景が霞み、消えてはまた現れ、景色に趣が加わるころ。春に出る霧は春霞(はるがすみ)と呼び、夜の霞は朧(おぼろ)と呼びます。月も霞がかかり美しい朧月となる夜は、時間がゆっくりと過ぎていくようです。
-
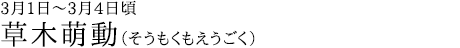
- 厳しい冬を超えてきた草木が、暖かな雨に促され芽吹き出すころ。この時期に降る雨を「木の芽起こし」といいます。厳しい冬を超えてきた生命の息吹を感じながら、緑鮮やかな菜花と旬を迎えた蛤のすまし汁で、春の訪れをかみしめてはいかがでしょう。