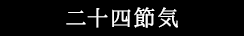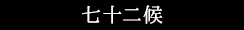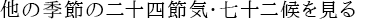日本人は昔から季節感を大切にして暮らしの中に取り入れてきました。
節分を基準に一年を24等分に分け、春・夏・秋・冬などの名称を付けたのが
「二十四節気」
です。
そして、その二十四節気の節気ひとつひとつをさらに三区分し、季節の風物を言葉で表現したものが
「七十二候」
です。
あなたも、日々の暮らしに、四季の移ろいを取り入れて、心のゆとりを感じてみませんか?

木枯らしが吹き、冬の訪れを感じるころのこと。
この日から立春の前日までが暦の上では冬となります。太陽の光が弱まって日も短くなり、木立ちの冬枯れが目立つようになります。
-
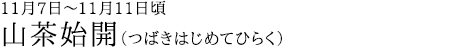
- 山茶花(さざんか)の花が咲き始めるころ。椿と混同されがちですが、先駆けて咲くのは山茶花です。垣根にぽつりぽつりと花をつけ始め、冬の訪れを予感させてくれます。
-
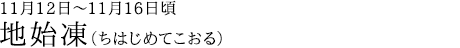
- 大地が凍り始めるころ。夜間の冷え込みもいっそう激しく、冬になったことがはっきりと肌で感じられる時期です。
-

- 水仙が咲き芳香を放つころ。「金盞」は金の盃のことで、春に咲くキク科の「金盞花(きんせんか)」ではなく、水仙の黄色い冠を見立てています。

木々の葉が落ち、山には初雪が舞い始めるころのこと。
「小雪」とは、冬とは言えまだ雪はさほど多くないという意味で、冬の入口にあたります。
-
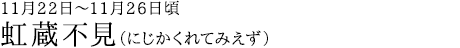
-
陽の光も弱まり、虹を見かけなくなるころ。「蔵」には潜むという意味があります。
昼の時間が短くなり、ますます冬らしさが増していきます。 -
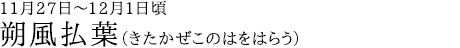
-
北風が木の葉を吹き払うころ。「朔風」は北の風という意味で、木枯らしをさします。
地面いっぱいに落ち葉が広がっていき、それとは対照的に枝は寂しくなっていきます。 -
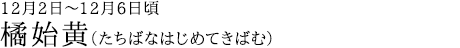
-
橘の実が黄色く色づき始めるころ。常緑樹の橘は、永遠の象徴とされています。
古事記や日本書紀の中でも、不老不死の実として登場します。